【脱党支援センター2020年10月19日】
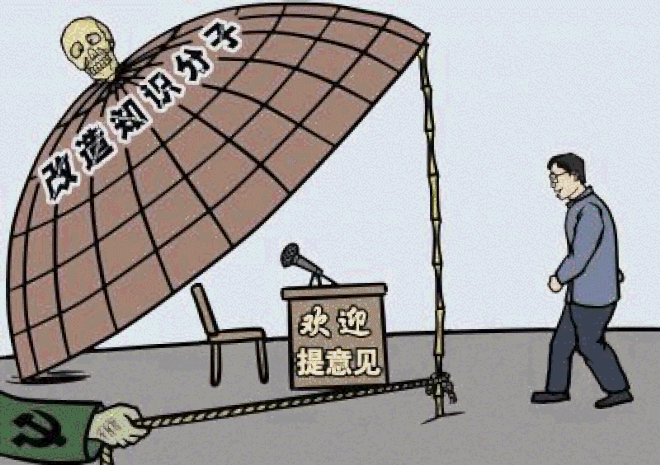
1-1)-(2) 知識人を批判する
『左伝』いわく、「最も上等なことは社会のために良い道徳基準を立てることであり、その次は国のために軍功を立て、さらにその次は後世のために優秀な文学作品を残すことである。時間が経っても廃れることがなく、これを不朽という」。中国の伝統文化は、知識人に大きな歴史の舞台を提供し、それらはきら星のごとく、人材が傑出していた。
そのため、知識人を改造することは、中共によって重要な一歩とみなされた。中国の伝統的社会は、「士、農、工、商」の四つの階層を重んじ、そのうち「士」とは知識人であった。「士大夫」階層とは道統の継承者であり、このため道徳の角度から言えば、彼らは統治者よりも発言権があった。
中共は、知識人が正当な道徳観念を代表しているとは認めていないが、知識人を介して庶民の思想を改造する必要があった。そのため、政権を取った中共がまずしなければならなかったことが、知識人の思想改造であった。
1950年6月、毛沢東は中共の第七回三中全会で知識人について言及し、「彼らを用いると同時に、その教育と改造を行わなくてはならず、彼らに社会発展史、歴史唯物論等を学ばせなければならない」とした。
毛のいわゆる教育と改造とは、中高・大学の教師に政治協商会議の三大文献と社会発展史と新民主主義を学習させるほか、1951年の秋から、大勢の知識人を「抗米援朝(アメリカに抵抗し、北朝鮮を支援する)」「土地改革」「反革命の鎮圧」に参加、参観させた。ここで知識人らは、血腥い政治運動を目の当たりにして共産党の残忍さを知ることとなり、多くの人たちが精神的に骨抜きとなってしまった。
1952年1月、全国政治協商会議常務委員会は『各界の人々を思想改造する運動に関する決定』を作成し、思想改造された知識人を全国に向かわせてその思想を推し広め、あらゆる人の思想を改造した。
清朝末に科挙が撤廃されて以来、知識人の多くが政党に付き従うようになった。これは苦しい過程であり、知識人が「自ら」思想転向を行う過程でもあった。
ただ、この種の転向は中共から見れば十分だとはみなさなかった。なぜなら、知識人は民主と科学の大旗を掲げる必要があると思っていたが、その一方で、儒家の修身立命の学が依然として是非を判断する基準と考えられており、それはまさに中共が容認できないことであったからである。
毛沢東は、1939年12月に発表した『中国革命と中国共産党』の中で、知識人を「小資産階級の範疇」であると書いた。あの階級闘争が盛んな年代であっては、このような「小資産階級」のレッテルを貼られた知識人は再起できなくなった。
中共は宣伝機関を通じて労働者と農民を賛歌し、彼らの知識の乏しさを革命の原動力とみなし、「素朴な階級の恨み」に共産党の指導があれば、革命を勝利に導くことができると宣伝した。その一方で、知識人は映画のなかで、眼鏡をかけびくびくし、書物にかじりついて大衆をかえりみず、何をするにも主観的である等々と描かれた。
1958年の映画『上海の娘さん』は、公開後にまもなく厳しい批判を受けたが、その原因は次のようなものであった。「第一に、党書記や支部書記による指導・教育がない中、知識人は大胆にも原則を堅持し、建設中に自己の才能を発揮している。これは党の指導を取り消し、党の指導に反するものだ。第二に、知識分子の軟弱性、動揺性、現実からの乖離、人民からの乖離などの欠点が描かれていない。これは、資産階級と知識階級を美化するものである。第三に、(中略)主人公は、労働者の中の堕落した思想の影響を受けて、目の前の功利を求めるようになったと描かれているが、(中略)これは、労働者階級に泥を塗るものだ」。このうち、第三の原因は、労働者と知識人の関係を挑発するものでもあった。
これらの知識人を侮蔑する宣伝は大きな作用を果たした。なぜなら、知識人はそれまでずっと社会の論調の指導者であり、社会問題に対する発言者であり、伝統文化の継承者であるとともに論述者であったのが、その形象に泥が塗られてからは、彼らの代表する価値観もまた転覆していったからである。大衆の眼には、知識人はもはや、尊敬され教えを請う対象ではなくなり、あざ笑われ、批判される対象となったのである。
もし上述のような侮蔑が「名誉上の毀損」であるならば、知識人の生業を絶つことは「経済上の遮断」であり、反胡風運動から反右派運動、文革までは知識人の「肉体上の消滅」の一部であったと言える。
中共の政権奪取時に生死を共にし、互いに助けあった民主派らは自らを本当の開基立業の功臣であると認識していた。このため、「肝胆相照らし、栄辱を共にした」中共もまた、彼らの強烈な社会的責任感と高大な抱負が十分に発揮できる機会を与えてくれるものと思っていた。
意見を述べるようにという「真心からの」要請に応える形で、「士は己を知る者のために死す」という崇高な考えを持った義士たちは、競うようにして大義慄然と意見を述べたが、結局、皆あまりにも悲惨な結末を迎えたのであった。
人々は中共のなすところを目にして、「党の天下」が何を意味するのか、十分に理解したのであった。つまり、「人民民主専制、あるいは人民民主独裁」ということであったのだ。
章伯鈞、章乃器、羅隆基、儲安平……等々の著名な文士は、愛国のため留学から帰国した博士であれ、財を共産党に投げ打った資本家であれ、大臣、教授、文学者、編集長、記者の地位からことごとく共産党の右派カテゴリーに放り込まれたのだが、彼らには、「民主」「と「独裁」が党によっていかに「人民専制」に結合されうるのか、冷酷な現実の中でどうにもはっきりさせることができなかったのである。
中国は悠久の歴史上で、「精忠報国(忠をつくして国に報いる)」、「捨生取義(生を捨てて義をとる)」「人格尊厳」「先に天下を憂いて、後に天下を楽しむ」などの伝統的な品格があったが、これらはすべて、彼ら末代の鴻儒博学の士の孤独な死とともに歴史上の舞台から永遠に消え去った。
人々は恐怖のうちに、積極的にこの世の天国を掲げてそれを餌に誘った共産党がまず先に建立したのはこの世の地獄であった、ということをはっきりと目にしたのである。
運よく生き残った人たちは、それ以来戦々恐々として、もう二度と伝統的な価値を持ち出すことはなくなり、知識人としての独自の思想と人格を堅持しようともしなくなった。例えば、馮友蘭と郭沫若は、毛沢東に一言批判されただけで、驚いてすぐに自分の学術的な観点を変えてしまった。知識人にとって、独自の思想と人格を保つことは命がけのことであった。これらの虐げられることによって造られた知識人の内心の苦痛は、決して筆舌に尽くすことのできるものではない。
「知識人」は、かつてはある意味では、道徳と同義語であって、清貧、正義、知識、教養、権力におもねない、といったことを意味していた。ところが、江沢民の時代になり、党の官界にある役割が出現した。それは「政治的メーキャップ係」だ。文士の正統とは大いに異なり、彼らは政治の舞台で提灯を持ち、人をほめそやす職人で、補佐しているのは聖賢の君子ではなく、鶏鳴狗盜の輩(げすっぽい才能や特技をもっている人)である江沢民の類だ。
小銃や戦車で殺戮を繰り返したあげく、国際社会から制裁と譴責の荒波を受ける中で登場した江沢民は、政治的なドーランを厚ぼったく塗り上げる必要があった。そこで、この文士たちが考え出したのが「三つの代表」だ。彼らは政治上、国運を台無しにしたのみならず、道徳上でも知識人が具えているべき清廉潔白を汚したのである。
今日に至り、中国のいわゆる「専門家学者」はもはや、奥深い正統文化とその行動様式を継承する知識人ではなくなり、その中の絶対多数は、中共の無神論、階級闘争哲学、社会発展史によって洗脳されている。彼らはただ科学技術の専門技術者であるだけで、正統文化である儒佛道の文化を深く研究したこともなければ、それを生活に取り入れたこともない。
今の中共は「知識を尊重し、人材を尊重する」をスローガンとして打ち出し、「党の恩は海のように広い」という演出をし、偽知識人が精一杯、複雑な理論を作り出しては中共統治の合法性、または後を絶たない社会の悲劇の合理性を論証しているにすぎない。
中共は「政治精鋭、経済精鋭、文化精鋭」の強固なトライアングルを作ることに成功したが、それに必要なのは、炭鉱事故で死亡した労働者に、「中国で生まれたからだ」などと平気で言える何祚庥のような「知識人」であった。
また、一部の党文化にひどく侵された知識人は、人としての基本的な良知は持っているものの、憂国憂民の心はなく、報国安民の道で苦しむこともなく、ただ「体制内」の身分だけを争奪し、「体制内の改革」を要求し、ただ「体制内での解決」を求めている。
「体制内での解決」は、まず共産党の臣下であると称することにほかならず、共産党とその党文化が自己に対してコントロールする権限と随意に使用する権利があることを認め、一歩進んで少しばかりの発言権を得ることにしかすぎない。選択の余地のない社会環境の中で、旧ソ連文学と共産党の著作にどっぷりと浸かって成長した人は、自己の成長過程における寝食を惜しみ、それが毒薬であるとも知らず、共産党への理想を捨てることができず、社会のために声を挙げることもなく、中共が万悪の源であるということを人々がはっきり認識できるよう手助けすることもできない。
これらの人が中共に希望を託するやり方は、個人の徳行を用いて中共の醜さを覆い隠していることにほかならず、余命いくばくもない中共の命を延ばしているのである。
(続く)
転載大紀元 エポックタイムズ・ジャパン



